コラム

++コラム一覧++
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
あれから日本はどう変わった?
2015年3月号
新生日本の曙・明治から約150年が経った。その間日本は、西欧主導の国際世界において、急速にプレゼンスを増し、文化大国・経済大国としての地位を確保してきた。
…が、長い近代の歴史の中で、日本という国はふたつの不幸を引きずった。ひとつは、指導者に「ひとびと」という思想がなく、「国家」という観点にとらわれてきたことだ。江戸のひとびとは元気で闊達だった。指導者がどうあれ、それを跳ね返す強さがあった。しかし明治以降のひとびとは、その元気をなくし、「国家」という魔物に翻弄されてきた。その典型が軍国昭和の「欲しがりません、勝つまでは」で疲弊したひとびとである。
もうひとつは、国家の指導者が合理精神~算盤勘定を喪失したことだ。明治の創設者たちが確かにもっていた「冷静に算盤を弾く精神」を、1905年に日露戦争で勝ったと勘違いしたそのときから喪失してしまった。民の事を忘れ、合理性をなくしたことが、悪夢の30年間を招いてしまう。
1915年に、中国に21か条の要求をつきつけて、帝国主義の真似事を始めたあたりから1945年(昭和20年)の敗戦までの30年間は、間違った羅針盤による誠に悪夢の期間であった。
しかもその悪夢は、独裁者なき独裁によるもので、責任をとる者が誰も居ないという、奇妙奇天烈なもので、陰に陽にそのままズルッと現代に引き継がれている。そして、何か不都合があっても、誰も責任をとらない鵺(ぬえ)的体質のせいで、日本は、あだ花経済のバブルが崩壊した1991年ごろから羅針盤を失い失速してしまい、あれよあれよという間に、不毛の「失われた20年」に突っ込んでしまった。
つまり、1915年から現代までの100年のうちの50年は、悪夢と不都合の歴史であり、不幸なのは、なぜそんな50年間を持ってしまったのだろうという解明がなされないまま、いままた、混迷の中にあることであり、またぞろ同じ過ちを犯しかねないことである。
私たちは、日本社会の主役は「ひとびと」であり、国家を語る官僚ではないこと、そして日本社会は、弱肉強食の非情な国際社会において、合理的でしたたかな算盤勘定で切盛りされなければならないことを、しっかりと心に刻んでおこうと思う。
未曽有の課題に直面させられている日本。1000兆円(全国民1人当たり800万円)もの国家の借金、経済の沈滞化と長期化したデフレ、人口急減の中で進む急速な高齢化、日本力の源泉だった「中間層」という宝物の喪失と格差拡大、近隣国家との緊張の激化、そして風光明媚の源であった火山マグマの活発化と大地震の恐怖等々、どれもこれも一朝一夕に解決できない課題ばかりである。誰が、いったいどこの誰が、自らを鞭打ち、これらの課題に立ち向かっているのか。もしかしたら、誰もいないのではないか?
そんな中で私たちは、一体何をどうしたいのか、自分の世代さえよければよいのか、孫の世代に備えて何ができるのか、そして誰に何を託したらよいものかを、今日日の喫緊の課題として悩み抜かなければならないときに来ていると思う。
そんな思いで、2009年6月に、日本社会のあり様を問うたことがあった(よ~そろ・申し上げたき事あり「国の生業の形が違う」)。その直後に民主党政権が誕生し、いま、ひさしぶりに明確な所信をもつ安倍政権の時代となった。「ひとびと」にとって棲み良い日本という観点から、2009年以来の5年強で、何がどう好転したのかしなかったのか…あらためて問い直してみたいと思う。
2009年6月号「よ~そろ・申し上げたき事あり」
■国の生業(なりわい)の形が違う
私は、塩野七生さんの古代ローマから、たくさんのことを教わった。ノーブレス・オブリージュを貫き通した、気高いローマのリーダーたち。血税で国を守る気概に溢れ、国政参加を怠らず、どんな苦境にもくじけなかった市民たち。現代の日本人は古代ローマ人を超えているか?私たちは一体、2000年の歴史から何を学習したのかと、恥ずかしさで心が震える。
ローマは、「異」を受容する世界帝国として1500年間も存続した。あのアメリカでさえ世界帝国としてはまだ100年にも満たない。そのローマも実は盛衰の繰り返しだったという。その間、苦境に陥ると「根本問題は何か」を直視し、根本問題解決のためには、古い革袋など惜しげもなく捨て去ったという。
そう、一体現代日本人にとって、根本問題とは何なのだろう?国の生業(なりわい)の形そのものに、心に深く巣食っている問題があるのではないか。
■生業(なりわい)の基本を質す:
生きものの歴史は弱肉強食の繰り返しだという。人間社会もそうだけど、一方で最大多数の最大幸福を得ようと努力してきたことも、人間社会の歴史的事実である。「弱肉強食から最大多数の幸せへ」が、人間社会の課題なのだが、このところ日本では、アメリカ流の弱肉強食が生業の形になってしまった。
何といっても社会の原点は、互いが気になる「向こう三軒両隣」であり、助けあいの「隣組「注①」だ。赤子の誕生を祝い合い、夜まわりも葬式もみんなでやった。村八分された者にさえ、最後の二分・火事と葬式は手を差し伸べる思いやりで、村の生業は成り立っていた。
いま、国を預かる中央政府は、この原点から乖離してしまった。行政は顔の見えない抽象事務で、助け合う喜びなどとは無縁な、強者のネクタイ事務でしかない。こんな他人(ひと)事事務は、可能な限り村や町の仕事に鞍替えしなければならない「注②」。村や町の役場にはまだ顔が見え、心を映し合えるから…。
<今回のコメント>
注① 日本では江戸の昔から、潤沢な「中間層」が社会の活力を生み出してきた。そして昭和の最盛期には、その中間層が世界も羨む「JAPAN AS NO.1」の地位と「企業村型フラット社会」を創り上げた。そこでは、会社と社宅で醸成される同等意識・同朋意識が共有されており、無慈悲で悲惨な競争よりも助け合いの精神に溢れていたと思う。 小泉政権の頃からか、アメリカ流のグローバリズム・弱肉強食の世界が蔓延りだして、中間層→勝ち組・負け組への解体現象を招来した。ちょうど原文を書いたころである。
そして今、安倍政権下で、中間層は金持ちと貧乏人に解体され、生活格差が大幅に拡大している。中間階級と自称する層が、自らを社会の主体者と自認し、社会をきりもりしてきたこれまでの日本。いま日本は、格差を当然とする世界の各国のように、「社会はいったい誰のためのものか?」…が問われなければならない普通の国になってしまったのだろうか。
「ふるさと創生」という新たな言葉も創設されたが、中央の官僚世界をどう解体し、地方主権をどう確立するのか、まだ何の処方箋も登場していない。この課題は、官僚制の解体の目処が立たない限り達成不可能なものである。

■官僚制の解体:
国の行政は官僚制という権力構造に依拠しているが、官僚制は制度疲労でもはや「死に体」である。省益あって国益なく、私欲あって倫理なしで、何より小理屈で凝り固まって、ロボット語でしかしゃべれない人種の巣窟で、変革を拒否するところに最大の悪がある。
もともと官僚制は、国益をあずかり、国民に尽くしてくれるという約束でつくられた大仕掛けな体制だが、いまや小利と保身と他人(ひと)事で贅肉だらけだから、解体すれば国の財政は30%も豊かになる。これでもかこれでもかと、官僚制の非常識と無駄を見せつけられてきた庶民の誰もがそう思っている。本当は官僚も族議員もとうにわかっている。わかっているのに抵抗するのは犯罪である。
■国民参加を:
日本の庶民は怒らない。官僚や政治屋から犯罪的なことをされても怒らず、物言わず、無表情で通してきた。しかしこのところ、さすがに事情がちがってきた。「もう許せない」、「官僚制は解体だ」と言い始め、問題が鮮明になってきた。
政権交代させて、官僚制と戦わせる「注③」。官僚制の牙城に政治がどこまで迫れるかは疑問だが、刀尽き矢折れれば、それはそれで国力の実態なのだから仕方がないと、国の衰退を受け容れるしかない。シナリオはこんなに明確なはずだった。
しかし、やっぱり日本の国民は不幸だ。国の生業の形を変えるせっかくの潮目が来ているのに、もう問題が見えなくなってしまっている。野党の古い体質と変革能力不足が露呈し、とても官僚に太刀打ちできそうもないと国民が諦めだし、一方で15兆円の大盤振る舞いをする与党に、国民の心は擦り寄り出している。目くらましのお金をもらって国民の心は拡散して、変革のエネルギーが矮小化しつつある。
<今回のコメント>
注③ 国民は見事にこの課題を実行に移した。民主党政権の誕生だった。しかしこの政権は、官僚制との対決姿勢は打ち出したものの、官僚制のもつ隠然たる実力の恐ろしさを認識さえできず、つまみ食いしただけで、完敗して課題を放り投げてしまった。この体たらくで「もう官僚制の打破などできっこない」と、国民を絶望させてしまった民主党は、国賊的であった。
そして新たな政権には、官僚の思惑の上に乗っかるだけで、官僚制の弊害打破など、ただの一度もしてこなかった自民党が座っている。日本の真の活力を封じ込めてしまっている官僚制…これを打破する目処がまったく立たないままの今の日本は、次代に向けて、山積する課題を先送りしてしまうしかないのだろうか。
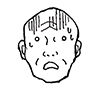
困ったものだ。どうしたらいいのだろう。政党という皮袋が古くなってしまったのなら、ローマの民がそうしたように、古きを捨てて、新しい革袋をつくるしかない。政界再編だ。再編のキーは「年齢」である。次世代のための国づくりだから、余命短く、汚れ過ぎた古だぬき議員にまかせてはいけない。清潔で馬力があって、冒険心に富む若者にこそ託すべきだ。国民の心が拡散し、問題が見えなくなった今、民意を結集するキーワードは、「若者にこそ託そう」だろう。選挙に行こう!そして今度の選挙はシンプルに行こう!年齢で投票だ「注④」。そして志ある若者に期待するしか残された道はない。…神様仏様ご先祖様だ。
<今回のコメント>
注④ 国家百年の大計…国の切り盛りは、百年先を見据えて行われなければならない。50年後にはこの世に居るはずもない50歳代以上のひとたちが、おのれと無縁の百年後のために骨身を削ってくれるなど、期待できるはずがない。国の借金を1000兆円もつくりながら、議員定数削減をさえ真面目にやろうとしない年配議員たち。ならば国家の大計は、難問山積の中で50年を生きざるを得ない若者世代にこそ託すしかないだろう。ずいぶんといい思いをしてきた年配者は、もう若者の頑張りに譲ってもいいだろう。この理の当然が、当然でない現実…いまだに国会議員の3分の2は、50歳代以上が占めている。
[現在の構成]→[望ましい構成] 
29歳以下:1人
30歳代:63人 33%→67%!
40歳代:174人
………………………………………………………………………
 50歳代:238人
50歳代:238人
60歳代:179人 67%→33%!
70歳代以上:65人
■商品の価値を質す:
生活は本当に便利になった。しかし贅沢の代償として、地球の人間圏が確実に壊れている「注⑤」。このままだと、地球の人間圏はあとわずか100年しかもたないと専門家はいう。温暖化の影響で、あのベネチアの街までが沈み始めている。地球の余計者である人間が、欲望追及に節度を忘れてしまった罰である。今、商品というものの意味を根本から問わねばならない。車から120km/h超のメーターをどうして外せないのか…化学洗剤や抗菌スプレイの垂れ流しがどうして清潔なのか…過剰包装のどこがどんなにおしゃれなのかetc.…問い質す事がまわりに溢れている。誰がどんな魂胆でこんな商品を押しつけているのか…国民はもっと急速に賢くならないと、地球から見放される。
<今回のコメント>
注⑤ 地球の温暖化による弊害については、一時期、「逆に地球は氷河期に向かっている」として、温暖化を否定する説が出てきたこともあったが、地球温暖化が、深刻な異常気象を来しながら確実に進展していることを、もはや誰も否定できない所まで来ている。
世界の中で44%もの二酸化炭素を放出している中国(27%)と米国(17%)は、ポーズはともかく真面目に排出量規制に向かってはいないし、日本は原発問題で、排出量が増加して、温暖化現象は、世界中を襲っている異常気象を深刻化させながら、地球の人間圏を確実に壊していくことだろう。
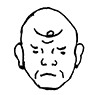
■経済は汗を流してナンボのもの:
貨幣を発明して人間の生活は便利になった。しかしそれに心を奪われる破目にもなった。
貨幣は目的か?!交換手段であるはずだった貨幣は、欲望を刺激し、際限なく人間の心の中を埋め尽くすようになってしまった。
人間社会の葛藤は、この貨幣の悪魔性と利便性の狭間で繰り返されてきた。報酬とは、汗を流してモノをつくる見返りというのが原点である。貨幣の一番の悪魔性は、汗を流さずにいくらでも儲けられ、汗を流さずにいくらでも貪欲であり続けられる点にある。貨幣や金の発明が、悪魔性を距離の限界を超えて解き放った。しかし現物貨幣や金という物質を媒体としている間は、この悪魔性には歯止めがかかってもいた。…が、バーチャル金融商品の登場で、この悪魔性は、時間軸の制約をも超えて虚無の世界に一挙に暴走し始めた。
今その悪魔性は、サブプライムローンの綻びをきっかけに最大となり、世界を壊しかねないところまできた。私たちは、「経済は汗を流してナンボ」「注⑥」という原点に立ち返るしかない所まで来てしまった。
<今回のコメント>
注⑥ 2008年10月に米国から発した金融恐慌は、いったん、最悪の事態は回避されたが、その後もギリシャ、スペイン、イタリア、スイス等の国家経済破綻の危機として、陰湿にくすぶり続けている。
日本の安倍政権下でも異様な現象を来している。アベノミクスは、貸し借りの関係で成立ちトータするとゼロ」の投機市場で成立っている。株価が9,000円から18,000円に倍増したと鼻息が荒い。しかし肝心の実態経済では、実質賃金が減少し続けている。これまでのところ日銀は、大量の紙幣を印刷してドルを購入し、ドル高→円安を誘導し、株の買い越し高という実態需要とは何の縁もない危険なゲームをしただけの現象ではないか。株で儲けて一見潤った金持ち派、額に汗して働いて実質賃金の低下に悩む貧乏派に国民を二分化する格差社会が創出されつつある。 その上、安倍政権は、国家の財産で株式を買って運用するという、危ない橋を渡ってしまった。バーチャル金融の危機は、世界の奥深くに身を潜めている。スイスはこれまで紙幣を際限なく印刷し、スイスフラン安を徹底演出してきたが、このバーチャル金融の深淵の中に落ちこんで、紙幣印刷をギブアップした途端、異常なフラン高を来して、国家破たんの危機にある。日本がこの二の舞いをしないと誰がいい切れるのだろうか。
安倍政権は、恐ろしい投機マネーに勝てるなどという幻想を一刻も早く捨て去り、実態経済において生産性向上に資する公共投資を果敢に行って、実需の牽引に努めなければならないと思う。汗を流してナンボの世界亜への回帰である。
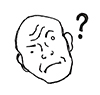
■どうやって国を守る…安全その1:
この60年、日本はアメリカに守ってもらった。そのありがたさの代わりに、アメリカのポチと呼ばれ、国内は米軍の基地だらけで、アメリカの属国の体にある。しかし最近は、アメリカ一辺倒からの脱却が言の葉に上り始めた。
自立意識の芽生えは大いに結構だが、またぞろ極端に走るのは危険である。いわく…アメリカはもう日本を守ってくれない。アメリカをやめて中国に尻尾を振っても救いはあるまい。いっそ核を持って、自力で守ろう…最近とみに増えてきた意見である。
国防は武器でしかできないか?外交音痴の日本人は、国防=武器保有と考えがちだ。平和ボケが知恵の力を忘れさせているが、国防の本旨はそもそも智力外交にある。世界ではいま、西欧中心の歴史の中でつくられてきた「格差」や「不条理」を是正しようという渦が巻き起こっており、世界を動かす主役は、もはや列強国ではなく、弱国の結束と世界の世論である。核保有大国が貧しい国々の顔色を見なければならない時代になった。
世界の世論を味方につける戦略戦術を、知恵を絞り抜いて編み出すことだ。外交の成功を支えるものは経済力であり、時に核をも凌ぐ力をもつ。まだ今なら日本の経済には力があるから、経済力を最大限に駆使して、乗り遅れている外交戦に一刻も早く加わることだ。
暴力で国を守ることは古来どこでもやってきた。今の日本なら、十分にそれができるだろう。しかしそれは唯一の核被爆国日本のとるべき道筋ではない。数千年の人間の歴史の中で、人間は安全確保のために暴力を使い、その度にみずからの業を恥じてきた。今、日本は、みずからの叡智を振り絞って、非暴力での安全確保の道筋を歩まなければならない「注⑦」。
<今回のコメント>
注⑦ その後、国際情勢は大きく変化した。膨大な軍備力を背景に中国が覇権・拡張主義をむき出しにする中、日本はこの中国と尖閣諸島問題をはじめ、対決の関係にある。かって周恩来副主席と田中首相は、この領土問題を後世まで棚上げするという外交の智慧で国交回復を果たした。
しかしいま安倍政権は、中国との対決を前提に、集団自衛権の是認、自衛隊派遣「恒常法」の制定、秘密保護法の設定、憲法改正に向けてまっしぐらに走っている。さらに、ODA援助さえも直接的に防衛と紐つけしつつある。
今日日の緊張関係の中である程度の防衛力の強化は必要である。…がしかし、国際関係を対決と置き換えて、武力で対処しようとするのは、算盤勘定に合わないもので、あまりにも単細胞的だと思う。対決より前に、敵をつくらないことに叡智を結集することこそ、外交の王道である。軍事に金を使う物入りの前に、日本の国是をあらゆる機会とツールを駆使して、世界の世論に発信することにこそ手間も金もかけるべきである。そして日本の大義に世界の世論が目を向けることになる。
中国の軍事力(1317億ドル)は、日本(545億ドル)の2.4倍であり、2014年の軍事力の伸び率は12%と異常である。この中国と際限のない軍事競争をやろうとするのは、非合理で無謀である。
外交はお互いを斟酌し合うことでもある。安倍政権はなぜ、現状の靖国神社参拝にこだわり、中国、韓国の反発を招くと、対決に処するに軍事防衛に走ろうとするのか。「分祀(本来の祀りの姿に戻すだけ)」という、祀りの本旨を確保した上で対外的にも納得的なソフトな祭祀の方法があるのに、自分流にこだわって自らを呪縛するのは稚拙である。どうして中・韓の目線国の眼差しが見えないのか。
日本は唯一の核被爆国…この日本のとるべき道筋は、剥き出しの軍事外交ではない。
日本社会の伝統的美徳である「多様性の受容」「真心」を基軸に、世界の国々にしたたかな平和外交を展開していかなければならないと考える。

非暴力での安全確保と平和ボケの他人(アメリカ)頼みの安全確保とは似て非なるものである。非暴力の外交は、研ぎ澄ました戦略シナリオに従って、経済力も手練手管もあらゆるものを動員して、世界の世論を味方につける「水鳥の水かき」の技である。冷徹な計算に涙ぐましい継続努力があってはじめて成り立つものである。至難の技だ。しかしこれこそ、人間歴史のネガテイブ・サイクルの中で、「非暴力・日本」の名が燦然と輝く栄誉の道筋ではないか。ローマが燦然と輝いている。そして日本も燦然と輝く。
■どうやって国を守る…安全その2:
無資源国・日本。だから資源を大型船で輸入して、商品を大型船で輸出する。日本はモノの通り道。日本はこの生業を選択する一方で、この50年、輸出依存体質からの脱却が急務と、常に叫ばれてきた。
しかし繁栄の極点に達したいま、輸出の牽引車・世界のトヨタが、何と1,500億円の営業赤字を出し、雇用の安全をも脅かしている。50年にわたって喫緊の課題と言われ続けた、輸出依存度の低減と国内市場の自立「注⑧」課題は、ほとんど手つかずだったわけで、今また、その「通り道経済」の脆弱さが露呈した。
<今回のコメント>
注⑧ 足の速い円安を背景に、トヨタが大赤字から脱し…の黒字を満喫する絶好調なのをはじめ、輸出企業が好調だ。国内消費は復調できないまま、国内市場はデフレで沈滞したままの中、日本経済はまたぞろ輸出に頼り切る従来の脆弱さを克服できないままである。円安で輸出が増えても、それ以上に輸入負担が増え、貿易収支は赤字基調である。モノの通り道・日本…モノの出入りだけでは、何も脆弱さは克服できない。国内市場の確立以外に、日本発展の王道はない。国内市場の拡大定着による雇用と所得の安定は、戦後から一貫して叫ばれてきた課題であるが、今日日いまだに、国内市場は低迷し、被雇用者の賃金は減少し、貧困層の増大を呼んでいる。
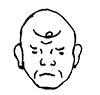
「通り道経済」は、50年間にわたって十分に役割を果たし、もう殿堂入りだ。次の選択をするにあたり、今改めて問うてみよう。日本は無資源国であるか「注⑨」。そんなことはない。この問いにこたえるには、発想の転換が必要だ。
石油や石炭、鉄鉱石はもっていない。しかし漫画やアニメをソフト資源と数えるまでもなく、資源は無尽蔵である。奥行きの深い文化力に風光明媚な観光資源、長寿社会への対応ソフトと技術力、公害防止、脱石油エネルギー化を支える精密技術などなど。
<今回のコメント>
注⑨ 日本の資源は、広義において無尽蔵である。しかし広義ではなく、従来の資源概念だけで見ても、日本が資源国になれる展望が開かれつつある。朗報だ。
これまでの資源は陸の地下の埋蔵を対象にしたものに過ぎなかった。海底の資源は、技術的限界があり、現実の資源として認識されてこなかった。…が、精密技術大国ニッポンは、その深海資源採掘技術を駆使して、近年次々と鉱床を発見している。そして先般、沖縄・久米島沖の水深1,400メートルの海底で、南米の鉱山の15~30倍の含有率をもつ新鉱床を発見した。発見者の浦辺東大名誉教授は「見たことがない高品位の鉱物で、驚嘆に値する」と興奮しているという。
海洋国家ニッポン、火山国ニッポン…日本は、火山国であることのツケを地震災害という形で背負わされておいるが、その一方で、火山大国である恩恵として、風光明媚の財産に加えて、資源財産を当てられた。この財産資源は、海洋国家であることに加えて、世界の追随を許さない深海資源採取技術あってのことである。
日本は狭義にも広義にも無尽蔵な資源国家である。

いやお米だってある。官僚の理不尽な政策が、全国を遊休地だらけにし、主食の自給率を危機的なものにしてしまった。誰が子供を「米嫌い」にしてしまったのだろう。おいしいお米は貴重な資源だ。おいしいお米をつくろう、野菜もつくろう。養魚もしよう。そして外国の森林を破壊せずとも、国内の森林のケアーをきちんとすることで、木材提供もできるだろう。コストが合うとか合わないとか、生業の形を工夫しさえすれば不可能はないはずだ。
お米も野菜も養魚も森林ケアーも、シニアが老後の充実に携わるのもよい。しかしもっとよいのは若者だ。フリーターだの3K嫌いだのと言ってないで、若者にこそ、この新たな資源創造を担って欲しい。汗を流してモノをつくる充実に、若者が目覚める。食料の自給率も高くなり、有資源国家日本のシナリオがひとつひとつ回転し始める。そして外圧に強い豊かな日本の生業の形が出来上がっていく。
<今回のコメント>
注⑩ 若者もシニアも各々元気で、汗を流して日本の現役で活躍してほしいと望んできた。…が今、格差社会への道を辿る中で、日本の宝「中産階級」は貧乏層にドロップアウト、老いも若きも元気を無くしている。日本社会の骨格が見えなくなりつつある。

■歴史の中に燦然と輝く日本を
日本は今、国の生業(なりわい)の形そのものに問題を抱えている。国民の幸せを盛るはずの革袋がほころびて、問題山積である。しかしもう少しも怖くないはずだ。「根本問題」は何かを直視すると、難しいはずの問題が、実は簡単に解けることがわかったから…。簡単なはずだけど難しいのは、私達自身が本気で「根本」を変えようと思うかどうかだ。問題は自分の中にある。これは難題だ。
しかしローマの市民はやり抜いたという。2,000年前のローマ人にできて、現代日本人ができない理屈などありようがないではないか。日本人よ、人間の歴史の中に燦然と輝けるチャンスを目の前にしている日本人よ、本気になろうヨ。ローマを超えて、幸せをつかもうヨ。【工藤】
